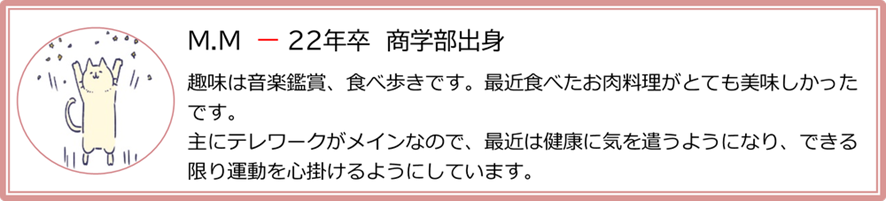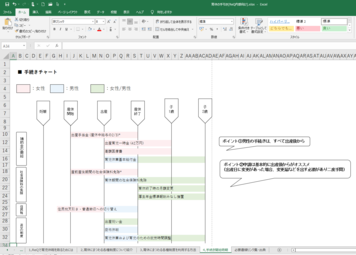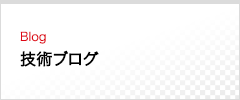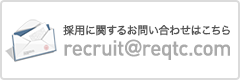第5回 文系女子、リモートワークに挑戦する。-メリハリ編-
こんにちは。2022年新卒入社のM.Mです。
前回のブログ「第4回 文系女子、リモートワークに挑戦する。-コミュニケーション編-」では、社員同士のコミュニケーションについてのお話でしたが、皆さんはリモートワークに対して少しでもイメージができたでしょうか?
今回はリモートワークの「仕事中のメリハリのつけ方」についてお話していきます。
わたし的リモートワーク環境!
はじめに、第4回ブログでN.Aさんも触れていたように、私がリモートワーク環境において用意したものを紹介します。
リモートワークで用意したもの
●広めの机
学生時代に使っていた机が少し狭かったこともあり、もう少し幅広い机を新調しました。やはり机が広いといろいろなものを置けるので、狭い机の時と比べて仕事の効率性も変わりました。
●PCスタンド
PCの高さや角度が変わり目線が上がるため、姿勢改善になりました。またPCスタンドの形状にもよりますが、私が購入したPCスタンドは下に空間ができるタイプのため、スペースの有効活用ができるようになりました。
これ以外に今後用意したいものは、椅子に敷く「クッション」と「外付けモニター」です。
最近少し腰が痛くなってきたなと感じているので、N.Aさんが言っていた「ゲルクッション」試してみようかな?とも思っています。
外付けモニターは以前会社に出社した際に使ってみたのですが、たくさんのアプリ画面を開いてもわかりやすく、仕事の効率が大幅にアップしたのでぜひ欲しいです!
仕事中のメリハリのつけ方
学生時代は「時間割」に従って授業を受けており、授業と授業の間の休憩時間にリフレッシュすることができていました。ですが社会人になるとそういった「時間割」というものは与えられないので、自ら時間管理を行わなければなりません。
私は時間管理をする上で大事なことは、仕事の中でメリハリをつけることかと考えています。そのため、3つ意識して行っていることがあります。
1つ目は、仕事始まりに「今日のタスクを書き出し、時間を決めて終わらせる」ことです。以前、あまりそういったことを意識せずに仕事をしていた際、仕事が長引いてしまうことがあり、リモートワークの中でだらだら仕事をしてしまうことを防ぐためにもそのような時間管理はとても有効だなと感じました。
2つ目は、業務上の「報連相をしっかりする」ことです。仕事をする上で基本的なことであり、チームコミュニケーションとして行いますが、私の場合はもう一つの意味として"ゴールを明確にするため"でもあります。報連相を行うことは、長いタスクを短いステップに分けることで中間のゴールが見えやすくなり、仕事に対してのモチベーションにもなります。
3つ目は、「運動」することです。リモートワーク中は体を動かす時間が減るため運動不足に陥りがちです。特に一日中座り続けていると体が凝って、集中力が切れてくるので、休憩中にストレッチや業務後に軽いジョギングなどを行い、なるべく体を動かすようにしています。
仕事と私生活の切り替え方
リモートワークは基本的に自宅での仕事になるので、入社当時は朝起きた後や昼休憩後に仕事モードに切り替えるなど、プライベートと仕事のオンとオフの切り替えが難しいと感じていました。
これまでいろいろと試してきましたが、オンオフの切り替えで一番効果があったのが、「勤務開始時に仕事用の服に着替える」ことでした。
仕事用の服といっても、もちろんスーツのようなきっちりした服というわけではなく、私はシンプルな色合いのオフィスカジュアルな服を着るようにしています。仕事用の服に着替えることは、着替えないときに比べて仕事に対して気が緩みにくく、やる気度が違うように感じます。あと切り替えとは関係ありませんが突発的な打合せにも慌てず対応できます!(心当たりのある方はいるのではないでしょうか...?)
このほかに聞いた話ですが、「仕事場を普段の部屋と変えること」で気分も仕事モードにチェンジでき、切り替えには効果的だそうです。私の上司も関東を離れて"ワーケーション"をしていたので、私もちょっとやってみたいなと思いました。(ワーケーションは、本ブログを執筆している2022年11月時点ではまだ導入検討段階です。)
今回は、リモートワークでどのようにメリハリをつけているか、モチベーション維持をどのように行っているかについて紹介しました。少しでも参考になりましたら幸いです!
ちなみに、仕事に全力で取り組みつつ、時には休憩も必要です。私は好きな紅茶を飲んだり、家猫をなでたりしてリフレッシュをしています。これも一つの「メリハリのつけ方」...?かも。
次回▶▶第6回 文系女子、IT情報をリサーチする。
前回▶▶第4回 文系女子、リモートワークに挑戦する。-コミュニケーション編-
執筆者プロフィール